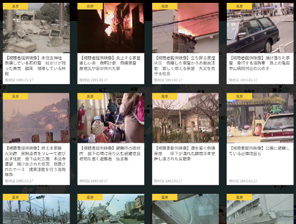映像を未来に伝えるために進めた「若手へのバトンパス」
特集:阪神・淡路大震災から30年
(株)エー・ビー・シー リプラ
木戸崇之
2025年3月1日
「朝日放送のライブラリーには、阪神淡路大震災の時に視聴者から提供された映像が40 本ほどある。これをもういちど掘り起こして、震災アーカイブに入れたいんやけど、その作業を頼めへんかな?」去年の春、筆者は若いスタッフに“無茶ぶり”した。
筆者が勤務する朝日放送グループが「激震の記録1995 阪神淡路大震災取材映像アーカイブ」(https://www.asahi.co.jp/hanshin_awaji-1995/)を開設したのは2020 年1 月、震災25 年の節目だった。放送局がなかなか踏み出せなかった災害映像の社会還元。その障害の一つである“肖像権”についてポリシーを大きく転換し、2000 クリップ約40 時間の取材映像を公開した。災害報道に対する拒否反応も小さかった1995年の都市型震災は、今では考えられないほど被災者のことばや表情がしっかりと映像に収められていて、多くの教訓を学び取ることができる。講演や出前授業はもちろん、コロナ禍で校外活動がままならない中での防災教育教材としても活用された。視聴する子どもたちの心理的負担を必要以上
に大きくしないよう、映像を選んで作ったe ラーニングサイトは、教育現場で広く使われている。
変化の激しいインターネット空間では、放っておくとWeb サイトはあっという間に陳腐化し、いつの間にか見られなくなってしまう。あの手この手でバージョンアップを繰り出す中で、次なる核として選んだのが「視聴者提供映像」だった。
提供映像は、報道のカメラがなかなか入り込めない場所の様子を映し出す。局から遠く離れた被災地のど真ん中だったり、家の中だったり。激しい揺れを経験した人がカメラを持っているので、息づかいも生々しい。ただ、局のカメラマンが撮った取材映像と異なり、提供映像の著作権は視聴者にある。30 年前、「放送に使って……」と局に持ち込んだ映像を、30年経ってホームページで公開するためには、もういちど提供者を探し出す必要があった。
あえて「ポスト震災世代」に作業を託す
報道記者経験がある筆者(52 歳)なら家捜しのノウハウもあるし、効率よく探せるだろう。でも私のような世代が“既得権”として「阪神淡路」を握り続けたら、若者はいつまで経ってもそのポジションを引き継げない。30 年の節目は良い機会だ。職権を使ってあえて無理矢理、部下にバトンを渡してしまおうと考えた。指名したのは、普段映像を管理しているアーキビスト。福岡県出身で記者経験もなく、阪神淡路大震災の時は生まれてもいない26 歳である。
彼女は、記録にある連絡先に電話をした。怪しい電話といぶかしがられ、信用してもらえなかった。電話がつながらない時は、他のスタッフと手分けして住所を尋ねた。表札が変わっていたら、ご近所やマンションの管理人さんなど、転居先を知っていそうなひとを探した。ネット上で同姓同名を見つけると、そのお店にまで出かけて聞き込みをした。まるで探偵のような作業の末、半数超の22 人が判明。うち21 人から公開の了承をとって、当時の状況をヒアリングしてくれた。その後の映像整理はむしろ彼女の本業だ。
成果はWeb サイト「激震の記録1995」での公開にとどまらない。書籍『スマホで見る阪神淡路大震災』(西日本出版社)の増補改訂版には、映像に飛べるQR コードだけでなく、彼女が聞き取った撮影の背景エピソードを掲載した。また朝日放送テレビが制作した30 年特番「あの時から今へ 私が撮った1.17」でも、この提供映像を撮った視聴者の30 年に焦点を当てた。アイドルグループ「Aぇ!group」の佐野晶哉さん(西宮市出身・22 歳)が提供者らのもとを訪ね、撮影したときの想いやその後の30 年を聞いてくれた。スタッフも若い世代で固め、苦労しながらも自分たちならではの視点を見つけ出し、新鮮な番組に仕上がった。
関西では今年、「いのち輝く未来社会のデザイン」をメインテーマに万博が開催される。その大前提は、“災害で命を脅かされない社会”だ。弊社は「災害を伝える」ことをテーマに、9 月1 日からの防災週間に万博会場内でイベントを構え、「AI による震災アーカイブの高度化」などを未来に提案する予定だ。イベントをともに盛り上げるパートナーを広く募って、ともに「いのち輝く未来」に貢献したいと考えている。“災害伝承30年の壁”は、伝え方の進化によって乗り越えていけると信じたい。